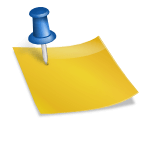2025年、日本の特撮ヒーロー番組の歴史に大きな転換点が訪れた。50周年という節目を迎えた「スーパー戦隊シリーズ」(テレビ朝日系)が、現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に放送終了することが明らかになったのだ。10月26日放送回の平均世帯視聴率はわずか1.9%。関連商品売上も仮面ライダーシリーズの5分の1にあたる64億円にとどまり、「制作費に見合わない」という厳しい現実が打ち切りの背景にある。半世紀にわたり子どもたちに夢を届けてきた伝説のシリーズは、なぜ終焉を迎えることになったのか。
50周年の節目で打ち切り:スーパー戦隊シリーズの衝撃的決断
1975年に「秘密戦隊ゴレンジャー」としてスタートしたスーパー戦隊シリーズは、日本の特撮番組史において最も長寿のシリーズの一つだ。5人(または3〜6人)のヒーローがチームを組んで悪と戦うという基本フォーマットは、50年間変わらず受け継がれてきた。色分けされたスーツ、巨大ロボットによる戦闘、そして「変身」という儀式。これらの要素は、世代を超えて子どもたちの心を掴んできた。
しかし、2025年という記念すべき50周年を迎えた今年、テレビ朝日は衝撃的な発表を行った。現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に、スーパー戦隊シリーズの放送を終了するというのだ。50作品目という節目の作品が、同時にシリーズ最後の作品となる。この発表は、ファンはもちろん、テレビ業界全体に大きな衝撃を与えた。
打ち切りの背景には、厳しい経営判断がある。テレビ朝日関係者によれば、「イベントや関連グッズ、映画化などで得られる収入が番組制作費に見合わない」という。実写特撮番組は、アニメに比べて制作コストが高い。俳優のキャスティング、特撮撮影、スタントアクション、そして巨大ロボットのCG制作。これらすべてに莫大な費用がかかる。それに見合う収益が得られなければ、継続は困難だ。
視聴率も低迷している。2025年10月26日放送の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の平均世帯視聴率は1.9%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。かつて10%を超えていた時代からは考えられない数字だ。子どもたちの視聴習慣が変化し、YouTubeやNetflixなどのストリーミングサービスに流れている現在、地上波テレビの視聴率低下は避けられない。しかし、それにしても1.9%という数字は、番組の存続を正当化するには厳しすぎる。
視聴率1.9%が示す厳しい現実:子どもたちはどこへ消えたのか
2025年10月26日、日曜日の朝9時30分。かつてこの時間帯は、多くの子どもたちがテレビの前に集まり、スーパー戦隊シリーズに夢中になっていた。しかし、この日の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の平均世帯視聴率は、わずか1.9%だった。ビデオリサーチ調べ、関東地区のデータだが、この数字は番組の置かれた厳しい状況を如実に物語っている。
視聴率1.9%とは、どれほどの規模なのか。関東地区の世帯数を約2000万世帯とすると、約38万世帯が視聴していたことになる。一見すると少なくない数字に思えるが、番組制作の経済性から見れば話は別だ。テレビ局は広告収入で番組制作費を賄う。視聴率が低ければ広告単価も下がり、収益は減少する。実写特撮番組は制作コストが高いため、視聴率1.9%では採算が取れないのだ。
かつてスーパー戦隊シリーズは、10%前後の視聴率を誇っていた。1980年代から1990年代にかけては、日曜朝の定番番組として多くの家庭で親しまれていた。しかし、2000年代に入ると徐々に視聴率は低下。近年では3〜5%台が常態化し、そしてついに1%台に突入した。この背景には、子どもたちの視聴習慣の劇的な変化がある。
現在の子どもたちは、地上波テレビを見ない。YouTubeで好きな動画を選んで見る、Netflixで海外アニメを一気見する、TikTokでショート動画を楽しむ。視聴体験は完全にオンデマンド化し、リアルタイムで特定の番組を見るという習慣そのものが失われつつある。さらに、スマートフォンやタブレットが普及したことで、テレビという媒体自体が子どもたちの日常から遠ざかっている。
関連商品売上64億円:仮面ライダーの5分の1という格差
スーパー戦隊シリーズの打ち切りを理解する上で、もう一つ重要なデータがある。関連商品の売上だ。テレビ朝日で放送されている「仮面ライダーシリーズ」も「スーパー戦隊シリーズ」も、関連する玩具やグッズを販売しているのはバンダイナムコホールディングスだ。同社が2025年5月に発表した作品別売上によれば、「仮面ライダー」が2024年通期で307億円だったのに対し、「スーパー戦隊」はその5分の1ほどの64億円にとどまっている。
この格差は、なぜ生まれたのか。仮面ライダーシリーズは、主人公が一人(または少数)のヒーローであり、キャラクターへの感情移入がしやすい。変身ベルトや武器といった玩具も、子どもたちにとって「自分も仮面ライダーになれる」という憧れを具現化したものだ。一方、スーパー戦隊シリーズは、5人のチームヒーローという構造上、特定のキャラクターへの集中度が分散しやすい。さらに、巨大ロボットの玩具は高額で、購入のハードルが高い。
さらに深刻なのは、市場環境の変化だ。かつて子どもたちは、テレビで見たヒーローの玩具を欲しがった。しかし、現在の子どもたちは、ゲームやデジタルコンテンツに興味が移っている。物理的な玩具よりも、スマホゲームやオンラインゲームに課金する方が魅力的なのだ。バンダイナムコの売上ランキングを見ても、トップは「ドラゴンボール」の1906億円。海外市場も含めた展開が功を奏しているが、これはアニメ作品だ。実写特撮番組の関連商品は、もはや市場の主役ではなくなっている。
テレビ朝日関係者は、こう語る。「仮面ライダーは引き続き好調ですが、スーパー戦隊は厳しい。関連商品の売上が伸びなければ、番組を継続する意味がない。広告収入だけでは制作費を賄えないのです」。テレビ番組と関連商品のビジネスモデルは、互いに支え合う関係にある。片方が崩れれば、もう片方も立ち行かなくなる。スーパー戦隊シリーズは、まさにその状況に陥ったのだ。
「制作費に見合わない」:実写特撮番組の高コスト構造
スーパー戦隊シリーズの打ち切り理由として挙げられているのが、「制作費に見合わない」という点だ。実写特撮番組は、アニメに比べて制作コストが圧倒的に高い。俳優のキャスティング、衣装制作、特撮撮影、スタントアクション、巨大ロボットのCG制作、ロケ地の確保、スタッフの人件費。これらすべてに莫大な費用がかかる。
特に負担が大きいのは、特撮撮影だ。爆発シーンや巨大ロボットの戦闘シーンは、CG技術を駆使して制作される。かつてはミニチュアや着ぐるみを使った撮影が主流だったが、現在は視聴者の目が肥えており、高品質なCGが求められる。しかし、高品質なCGは高コストだ。1話あたりの制作費は数千万円に達するとも言われている。
一方、アニメは比較的コストを抑えられる。テレビ朝日で放送されている「プリキュアシリーズ」は、関連商品売上が79億円と仮面ライダーには遠く及ばないが、「実写ではなくアニメなので『スーパー戦隊』に比べて経費がかからない。打ち切りはなさそうです」とテレビ朝日関係者は語る。アニメは、一度キャラクターデザインや背景を作成すれば、それを使い回すことができる。声優のギャラも俳優に比べれば安い。こうしたコスト構造の違いが、番組の命運を分けたのだ。
さらに、イベントや映画化による収入も、期待したほど伸びていない。スーパー戦隊シリーズは、毎年夏に映画を公開しているが、興行収入は数億円規模にとどまる。仮面ライダーの映画が10億円を超えることもあるのと比べると、差は歴然だ。イベントも同様で、動員数は減少傾向にある。こうした状況では、番組を継続する経済的合理性が失われてしまう。
仮面ライダーとプリキュアは継続:生き残る番組との差
スーパー戦隊シリーズが打ち切られる一方で、同じテレビ朝日の「仮面ライダーシリーズ」と「プリキュアシリーズ」は継続が決定している。この差は、どこから生まれるのか。最も大きな要因は、関連商品の売上とコスト構造だ。仮面ライダーシリーズは307億円と、スーパー戦隊の5倍近い売上を誇る。プリキュアシリーズも79億円と、スーパー戦隊を上回る。
仮面ライダーシリーズが成功している理由は、主人公が一人(または少数)という構造にある。子どもたちは、特定のヒーローに強く感情移入し、変身ベルトや武器といった玩具を欲しがる。さらに、仮面ライダーは大人のファン層も厚い。1970年代の初代仮面ライダーを見て育った世代が、今では40〜50代となり、自分の子どもと一緒に番組を楽しんでいる。こうした世代を超えたファン層が、安定した収益基盤を支えている。
プリキュアシリーズは、女児向けアニメとして独自のポジションを確立している。関連商品売上は79億円と、仮面ライダーには及ばないが、アニメであるため制作コストが低い。テレビ朝日関係者が語るように、「実写ではなくアニメなので経費がかからない」のだ。さらに、プリキュアは女児向けという明確なターゲット設定があり、衣装やアクセサリーといった関連商品が売れやすい。こうしたビジネスモデルの違いが、継続と打ち切りを分けた。
スーパー戦隊シリーズは、5人のチームヒーローという構造上、特定のキャラクターへの集中度が分散しやすい。さらに、巨大ロボットの玩具は高額で、購入のハードルが高い。実写特撮番組であるため制作コストも高く、収益性が低い。こうした複合的な要因が、打ち切りという結論につながったのだ。
50年間変わらぬフォーマット:5色のヒーローと巨大ロボット
スーパー戦隊シリーズの最大の特徴は、50年間ほぼ変わらないフォーマットにある。5人(または3〜6人)のヒーローが、それぞれ異なる色のスーツを着て、チームを組んで悪と戦う。赤がリーダー、青がクールな参謀役、黄色が明るいムードメーカー、ピンクが紅一点、緑が力持ち。こうしたキャラクター配置は、作品によって多少の変化はあるものの、基本的な構造は変わらない。
そして、もう一つの特徴が巨大ロボットだ。敵が巨大化すると、ヒーローたちもそれぞれのマシンを合体させて巨大ロボットに変身し、戦う。この「合体」のギミックは、玩具販売において重要な要素だった。子どもたちは、複数のマシンを集めて合体させることで、巨大ロボットを完成させる。この収集欲を刺激する仕組みが、関連商品の売上を支えてきた。
しかし、このフォーマットの変わらなさが、逆に時代遅れと受け取られるようになった。現在の子どもたちは、YouTubeで多様なコンテンツに触れており、50年前と同じフォーマットでは新鮮味を感じない。さらに、海外のマーベル映画やアニメなど、よりダイナミックで複雑なストーリーのヒーロー作品に慣れている。スーパー戦隊シリーズの「色分けされた5人のヒーローが悪と戦う」という単純な構造は、もはや時代に合わなくなっていたのだ。
ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー:記念作品が最終作品に
現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」は、スーパー戦隊シリーズ第50作品目という記念すべき作品だ。タイトルに「50(ゴジュウ)」という数字が入っているのも、50周年を意識したものだ。しかし、この記念作品が、同時にシリーズ最後の作品となる。皮肉にも、節目の作品が終焉の作品となってしまったのだ。
「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」は、過去49作品のオマージュやセルフパロディを盛り込んだ内容となっている。歴代のスーパー戦隊が登場するクロスオーバーエピソードも用意され、ファンサービスに徹した作品だ。しかし、それでも視聴率は1.9%にとどまった。記念作品であっても、視聴者を呼び戻すことはできなかったのだ。
ファンの間では、「せめて最終回だけは盛大に送り出してほしい」という声が上がっている。50年の歴史を持つシリーズの最終回は、単なる一作品の終わりではなく、一つの時代の終わりを象徴するものだ。テレビ朝日と東映がどのような最終回を用意するのか、注目が集まっている。
海外展開の失敗:ドラゴンボールとの圧倒的格差
バンダイナムコホールディングスの作品別売上ランキングを見ると、トップは「ドラゴンボール」の1906億円だ。この圧倒的な数字は、海外市場での展開が成功していることを示している。アニメ作品であるドラゴンボールは、言語や文化の壁を超えて世界中で愛されている。一方、スーパー戦隊シリーズの64億円は、ほぼ国内市場のみの数字だ。
スーパー戦隊シリーズも、海外展開を試みたことはある。アメリカでは「パワーレンジャー」として、日本の映像を流用しつつアメリカ独自のストーリーで展開された。1990年代には大ヒットし、日本にも逆輸入されるほどの人気を博した。しかし、近年はパワーレンジャーの人気も低迷しており、海外市場での収益は限定的だ。
海外展開が難しい理由は、文化的な要素にある。スーパー戦隊シリーズは、日本特有の「チーム精神」や「色分け」といった要素が強く、海外の視聴者には理解されにくい。さらに、実写特撮という形式も、CGが主流の海外市場では古臭く見える。アニメであれば、こうした文化的な壁を超えやすいが、実写特撮は難しい。この海外展開の失敗が、収益性の低さにつながったのだ。
日曜朝9時30分、静まり返ったリビングルーム
2025年10月26日、日曜日の朝9時30分。東京都内のあるファミリー世帯のリビングルームに足を踏み入れた。かつてこの時間帯は、子どもたちがテレビの前に集まり、スーパー戦隊シリーズに夢中になっていた。しかし、今日のリビングは静まり返っている。テレビは確かについているが、画面に映る「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を見ている人はいない。
父親はスマートフォンでニュースをチェックし、母親はタブレットでレシピを検索している。8歳の長男は、自分の部屋でNintendo Switchのゲームに夢中だ。5歳の次男だけが、リビングのソファに座っているが、その手にはiPadがあり、YouTubeで別の動画を見ている。テレビは単なる背景音になっており、誰も真剣に見ていない。これが、視聴率1.9%という数字の実態だ。
テレビ画面では、色鮮やかなスーツを着た5人のヒーローが、派手なアクションで敵と戦っている。爆発のCG、巨大ロボットの合体シーン、決め台詞。かつて子どもたちを魅了した要素がすべて揃っているが、今の子どもたちの心には響かない。父親に話を聞くと、「自分が子どもの頃は夢中で見ていたんですけどね。今の子どもたちは、YouTubeで好きなものを選んで見る方が楽しいみたいです」と苦笑する。
次男のiPadを覗くと、画面には海外の人気YouTuberが、巨大なレゴブロックでスーパーヒーローの基地を作る様子が映っている。カラフルな映像、テンポの速い編集、次々と変わる場面。スーパー戦隊シリーズの30分という枠組みに比べ、YouTube動画は10分程度で完結し、飽きることがない。次男に「スーパー戦隊は見ないの?」と尋ねると、「ちょっと長いし、つまらない」と即答された。
別の日、都内の大型玩具店を訪れた。スーパー戦隊シリーズのコーナーに足を運ぶと、巨大ロボットの玩具が並んでいる。価格は1万円前後。決して安くはないが、かつてこのコーナーは子どもたちで賑わっていた。しかし、今日は人影がまばらだ。一方、仮面ライダーのコーナーには、複数の親子連れが集まっている。変身ベルトを手に取り、「これ欲しい!」とねだる子どもの声が聞こえる。
店員に話を聞くと、「スーパー戦隊の玩具は、ここ数年売れ行きが厳しいです。仮面ライダーは安定して売れるんですけどね」と語る。理由を尋ねると、「仮面ライダーは変身ベルト一つで『ヒーローになれる』感覚がある。でも、スーパー戦隊は5人のロボットを全部集めないと完成しないから、親御さんも買いにくいんです」。確かに、5体のロボットを買い揃えると、5万円以上になる。この価格は、現在の家庭には厳しい。
夕方、都内のショッピングモールで開催されているスーパー戦隊のイベントを訪れた。ステージでは、ゴジュウジャーのメンバーがトークショーを行っている。観客席には、100人ほどの親子連れが集まっているが、会場のキャパシティからすれば半分も埋まっていない。一方、隣のフロアで開催されているゲームの体験イベントには、長蛇の列ができている。子どもたちの興味は、明らかにデジタルコンテンツに向いている。
📺 スーパー戦隊シリーズ50年の歩み:栄光から終焉への時系列
❓ よくある質問(FAQ)
Q1: スーパー戦隊シリーズが打ち切りになった最大の理由は?
A: 最大の理由は、「制作費に見合わない収益構造」です。関連商品売上が64億円と仮面ライダー(307億円)の5分の1にとどまる一方、実写特撮番組の制作コストは非常に高額です。さらに、視聴率が1.9%まで低迷しており、広告収入も十分に得られない状況でした。イベントや映画化の収益も期待値に届かず、番組を継続する経済的合理性が失われたのです。
Q2: 仮面ライダーは継続されるのに、なぜスーパー戦隊だけ打ち切りなのですか?
A: 仮面ライダーは関連商品売上が307億円と好調で、主人公が一人(または少数)という構造が子どもたちの感情移入を促し、玩具販売に有利だからです。変身ベルトや武器といった玩具は、一つで「ヒーローになれる」感覚を与えます。一方、スーパー戦隊は5人チーム構造で特定キャラへの集中度が分散し、巨大ロボットの玩具も高額で購入のハードルが高いのです。実写特撮という点は共通ですが、ビジネスモデルの違いが明暗を分けました。
Q3: 視聴率1.9%という数字は、どれくらい深刻なのですか?
A: 非常に深刻です。かつてスーパー戦隊シリーズは10%前後の視聴率を誇っていましたが、1.9%はその5分の1以下です。この視聴率では広告収入が制作費を賄えず、番組として成立しません。特に実写特撮番組は制作コストが高いため、視聴率3〜5%でも厳しいとされる中、1.9%は存続不可能な水準です。子どもたちの視聴習慣がYouTubeやストリーミングサービスに移行した結果と言えます。
Q4: 2026年3月以降の後番組はどうなるのですか?
A: 「週刊女性PRIME」の報道によれば、20代の刑事が主人公の新番組が検討されており、すでに制作チームが動き出してオーディションも開始されているとのことです。ただし、日曜朝9時30分はファミリー層向けの時間帯であり、刑事ドラマが適しているかは疑問視されています。テレビ朝日は刑事ドラマが得意ですが、この時間帯での視聴率獲得は難しいという指摘もあります。
Q5: プリキュアシリーズが継続されるのはなぜですか?
A: プリキュアはアニメであるため、実写特撮に比べて制作コストが圧倒的に低いからです。テレビ朝日関係者によれば、「実写ではなくアニメなのでスーパー戦隊に比べて経費がかからない」とのこと。関連商品売上は79億円と仮面ライダーには及びませんが、低コスト構造により収益性が確保できています。また、女児向けという明確なターゲット設定があり、衣装やアクセサリーといった関連商品が売れやすいのも強みです。
Q6: スーパー戦隊シリーズが復活する可能性はありますか?
A: 可能性は低いですが、完全にゼロとは言えません。将来的に、配信プラットフォーム(NetflixやAmazon Prime Video等)での展開や、低予算で制作できる新しいフォーマットでの復活が考えられます。また、大人向けのリメイクや、海外市場をターゲットにした展開も選択肢です。ただし、現在の収益構造のままでは復活は困難で、抜本的なビジネスモデルの変革が必要です。
50年の歴史が示すテレビ番組の宿命と変革の必要性
スーパー戦隊シリーズの打ち切りは、単なる一つの番組の終了ではない。それは、テレビというメディアの宿命と、エンターテインメント産業の構造変化を象徴する出来事だ。50年という半世紀にわたり、5色のヒーローたちは子どもたちに夢と希望を届けてきた。色分けされたスーツ、巨大ロボットの合体、決め台詞。これらの要素は、世代を超えて受け継がれ、多くの人々の記憶に刻まれている。
しかし、時代は容赦なく変化した。子どもたちの視聴習慣は、地上波テレビからYouTubeやNetflixへと移行。リアルタイムで特定の番組を見るという習慣そのものが失われつつある。視聴率1.9%という数字は、この変化の厳しさを如実に物語っている。かつて10%を超えていた視聴率が、わずか5分の1以下に落ち込んだ。これは、番組の内容が悪化したからではなく、視聴環境そのものが激変したからだ。
関連商品売上の低迷も、深刻な問題だ。64億円という数字は、仮面ライダーの5分の1に過ぎない。5人のチームヒーローという構造上、特定のキャラクターへの感情移入が分散しやすく、玩具販売に不利だった。さらに、巨大ロボットの玩具は高額で、購入のハードルが高い。現在の子どもたちは、物理的な玩具よりも、スマホゲームやオンラインゲームに興味が移っている。この市場環境の変化に、スーパー戦隊シリーズは対応できなかった。
一方で、仮面ライダーシリーズとプリキュアシリーズは継続が決定している。仮面ライダーは主人公が一人という構造が有利に働き、プリキュアはアニメであるため制作コストが低い。この対比は、ビジネスモデルの重要性を示している。エンターテインメント産業において、単に良質なコンテンツを作るだけでは不十分だ。収益性を確保できる構造を持たなければ、継続は困難なのだ。
スーパー戦隊シリーズの終焉は、テレビ業界全体に大きな問いを投げかけている。伝統的な番組フォーマットは、今後も通用するのか。地上波テレビは、どのようにして視聴者を取り戻すのか。デジタル時代のエンターテインメントは、どうあるべきなのか。これらの問いに対する答えは、まだ見つかっていない。しかし、一つだけ確かなことがある。それは、変化に対応できない者は淘汰されるということだ。
2026年3月、日曜朝9時30分の時間帯には、新しい番組が始まる。20代の刑事が主人公の番組という報道もあるが、ファミリー向けの時間帯で刑事ドラマが成功するかは疑問視されている。テレビ朝日の手腕が試される局面だ。しかし、どのような番組が始まろうとも、スーパー戦隊シリーズが築いた50年の歴史は消えない。多くの人々の心に刻まれた、5色のヒーローたちの勇姿は、永遠に輝き続けるだろう。
スーパー戦隊シリーズの終焉は、終わりであると同時に、始まりでもある。新しい時代のエンターテインメントがどのような形になるのか、私たちはその答えを探し続けなければならない。50年という歴史が示したのは、どんなに素晴らしいコンテンツでも、時代に合わせて変化しなければ生き残れないという厳しい現実だ。そして、その教訓を胸に、私たちは次の時代へと進んでいくのだ。5色のヒーローたちが残した遺産を、どのように受け継ぎ、発展させていくのか。それが、私たちに課された使命なのかもしれない。